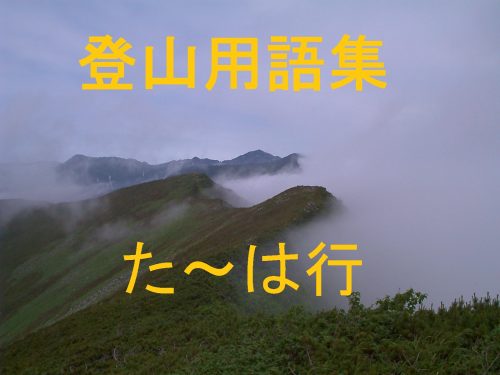初心者のための登山用語集221語
あ行(あ、い、う、え、お)
か行(か、き、く、け、こ)
さ行(さ、し、す、せ、そ)
あ行
あ
・アイスクライミング
氷壁、硬い雪の壁を登攀する技術。
・アイスハーケン
アイスクライミングに使用するハーケン。ロッククライミング用ハーケンと違い、氷用に特化して作られている。
・アイゼン
アイスバーンやクラストした硬い雪上を歩行するために登山靴に装着する金属の爪。クランポン。
・アイゼンバンド
ベルト式アイゼンを登山靴に固定するためのベルト。アイゼン本体とベルトが分離しているタイプと、アイゼン本体に固定されて付いている、固定ベルト式がある。ワンタッチ式アイゼンにアイゼンバンドはない。
・アイスバーン
雪面が完全に氷化した場所。
・アイスバイル
アイスクライミングに使用する短いピッケルのような道具。ピッケルと違い、ブレードがハンマー形状になっている。
・アタック
登頂をねらう時に使う言葉。
・アタックザック
ザックがキスリング型だった時代に、現在の縦長ザックをキスリングに対しアタックザックと呼んだ。
・頭
沢の源頭部の上にある、山頂よりやや低いピークをこのように呼ぶ。
・アックス
ピッケルの英読み。狭い意味ではクライミング用のピッケルを示す場合がある。
・雨具
カッパのこと。セパレート型、ポンチョ型、レインコート型などがある。
・雨蓋
ザック最上部の物入れになっている部分
・アーベンロート
夕日で雪山が真っ赤に染まる絶景のこと。朝日の場合はモルゲンロート。
・アーミーナイフ
スイスのビクトリノックス製軍用ナイフで、いわゆる小型のキャンプ用10徳ナイフ。
登山家や冬山愛好家が好んで使用する。
・アルバイト
登高する労力のこと。体力的にきついルートなど、アルバイトがきつい、アルバイトが強いられるなとど言う。
・アンザイレン
転落防止のため、パーティーのメンバーが互いにザイルで連結すること。
・鞍部
コル。ピークとピークの間のU字型になっている地形のこと。馬の鞍のように見えるのでこう呼ぶ。
い
・EPIガス
イギリス発祥のキャンプ用ガスコンロのメーカー。ガソリンや灯油式のコンロが主流だった時代にガスボンベ(カートリッジ)に直接バーナー部をねじ込んで使用できるタイプのガスコンロとしては歴史が長く、現在でも愛用者が多い。
・石突き
ピッケルのシャフトの下端にある金属の鋭く尖った部分。スピッツェ。
・一本立てる
小休止のこと。昔、立ち休憩する時に背負子の下部を棒で支えていたとされる。
・インソール
靴の中敷きのこと。現在では優れたインソールが多数あり、適切なインソールに交換することによって疲労度は大きく変わる。
・インナーシューズ
冬山用登山靴であるプラスチックブーツは二重になっていて、内側の靴をインナーシューズという。
・インナーシュラフ
シュラフの防寒・防汚を目的に使用する薄手のシュラフ。シュラフの内側に入れて使用する。新型コロナウイルスの影響(山小屋のシュラフをレンタルする場合に使用される)で需要が高まった。
う
・右岸
川の右側の岸。川は上流(水源)を背にして右岸、左岸という。
・浮き石
登山道で地中に固定されていない、踏むとぐらぐらする石のこと。
転倒の原因になるので、後続者に「浮き石注意」などと声をかける。
え
・エアーマット
テントや山小屋で寝る場合に、寝床に敷く空気式のスリーピングマット。
スリーピングマットは、この他にインフレータブル型、クローズドセル型などがある。
・エスケープ
アクシデントが発生した場合、予定を変更し、緊急下山したり、危険な場所の通過を回避すること。
・エスケープルート
エスケープするためのルート。長期縦走の場合はあらかじめエスケープルートを必ず設定しておく。
・えびの尻尾
冬山で強風によって木の幹や枝に樹氷が風上に向かって成長したもの。えびの尻尾のように見えることからこう呼ぶ。
お
・オーバーシューズ
冬山用登山靴の上からすっぽり履く布製の靴。特に寒さが厳しい山行に使用する。
・オーバーズボン
冬山で着用するアウターのズボン。スキーズボンのようなもの。
・オーバーハング
岩壁が垂直よりも手前に出っ張っている場所。
・オーバーミトン
冬山で使用する撥水された袖付きの2本~3本指タイプのナイロン製手袋。防寒用のインナー手袋の上から着用して使用する。オーバーミトンに対して、5本指タイプのものをオーバーグローブと呼ぶことがある。
か行
か
・カール
圏谷。氷食地形の一種。山肌をスプーンでえぐり取ったような特徴的な地形をしている。カールの底は平坦で良いテント場となる場合が多い。日本では、アルプスと日高山脈で見られる。
・カールバンド
カール底の平坦地から稜線の間の急斜面。
・概念図
地形図などの詳細図ではなく、山頂、稜線、沢などを線や記号で表した大まかな図。
・核心部
その山の行程中、最も緊張を強いられるような区間をこのように呼ぶことがある。
・肩
山頂より低い場所の顕著な平坦地。
・カッターシャツ
伝統的な登山用行動着。山シャツとも呼ばれる。デザインはYシャツ型でチェック柄が多く、胸ポケットには雨蓋が付いているのが特徴。素材はウール製だが、近年ポリエステル製が主流になっている。
・カッティング
つぼ足で硬い雪の斜面を歩行する場合に、ピッケルのブレードを使って雪面にステップを切る技術。
・滑落停止
雪山において、ピッケルを使用して滑落を止める技術。
・釜
滝つぼのこと。
・河畔林
沢の下流から中流域の両岸にある平坦で歩きやすい樹林帯。
・カラビナ
岩壁や冬山で登攀や下降などをする時に使用する連結金具。O型、D型などがある。
・ガレ場
砕けた岩の破片が堆積している斜面。沢の上流部などに多い。
・缶メタ
缶入りの固形アルコールで、五徳が付いており、コンロの代用(非常用)として使用する。固形燃料、携帯燃料、携燃(けいねん)などと呼ぶ場合もある。
き
・きじを撃つ
山で男性が野糞をする時の隠語
・きじ場
登山者がきじを撃つ場所。ほとんどの場合、きじ場には踏み跡があり、同じ場所が選ばれる傾向がある。
・キスリング
登山の草創期に使用していた、横長のザック。厚い帆布で出来ており、昭和60年代まで使用されていたが現在では見かけない。
・キックステップ
雪山の斜面をつぼ足で雪面を蹴って足場を作りながら歩行する技術。
・脚絆(きゃはん)
1 沢登りの時に脛を防護したり、足袋への異物侵入を防ぐために着けるもの。
2 靴内への異物の侵入を防いだり、脛を防護するものの総称。スパッツ、ゲイター、ゲートル。
・共同装備
登山パーティーの装備の中で、テントや火器などパーティーで共用する装備品。
・極地法
ベースキャンプや前進キャンプなど複数のキャンプを設営し、荷上げしながら登頂を目指す登山方法。
く
・草つき
沢登りで沢の両岸に木がなく、草が生えている滑りやすい急斜面
・くさり場
急な岩場や斜面などには安全のために、鎖やザイルが登山道に固定して設置されていることがあるが、そのような場所をこう呼ぶ。
・クラスト
雪山で日射や強風の影響で雪面が非常に硬くなっている場所。
・クランポン
アイゼンのこと。
・グリセード
ピッケルを杖にして、つぼ足のまま雪面をスキーのように滑り降りる技術。
け
・軽アイゼン
主に夏山の雪渓通過時や、雪山の低山などで使用される簡易的なアイゼン。本格的なアイゼンと違い、爪が短い、爪の本数が少ないなどの特徴がある。
・携帯トイレ
登山中の排泄物を持ち帰るための携帯型簡易トイレ
登山人口の増加とともに利用者が増えている。
・軽登山靴
主に日帰り登山など、比較的難易度の低い登山向きに作られた登山靴。トレッキングシューズと同じ意味で使われることもある。
・ケルン
岩や小石を積み上げた道しるべのこと。
・圏谷
カールのこと。
・懸垂下降
垂直な崖などを降りる場合に、ザイル、ハーネス、カラビナなどを使用して下降する技術。
ラぺリング、リペリングともいう。
・源頭部
沢の最上流部の水がなくなる場所。
こ
・高度計
標高を計測する装備品。登山においては、気圧を検知して高度を計測するものが多い。単体のものや、高度計付腕時計などがある。
・行動食
歩行中に食べる食事。飴やお菓子類などが好まれる。
・ゴーロ
沢登りにおいて、比較的大きめの石がごろごろしている場所。
・個人装備
登山パーティーで各個人それぞれが持って行く装備品。
共同装備に対してこう呼ぶ。
・コッヘル
コッフェル。アルミ製などのキャンプ用の簡易鍋。
・コバ
登山靴の靴底(アウトソール)のつま先とかかとの出っ張り部分のこと。
コバがない登山靴はワンタッチアイゼンの装着はできない。
・コル
鞍部のこと。
・ゴルジュ
沢の両岸が絶壁になっていて、沢幅が狭く通過が困難な場所。
廊下、函などと呼ぶ場合もある。
・コンパス
携帯型方位磁石のこと。登山ではオリエンテーリング用コンパス(コンパスと定規が一体になったタイプ)が好んで使用される。
さ行
さ
・ザイル
登山用に用いるロープ
・左岸
川の左側の岸。上流(水源)を背にして右岸、左岸という。
・サブザック
日帰り登山に使用する比較的リッター数の小さいザックのこと。
・サブリーダー
登山パーティーにおいて、リーダーの補佐役のメンバー。先頭を歩き、ルートハンティングを行うことが多い。
・ザレ
小石や砂地の場所(砂礫地)をこう呼ぶことがある。
・山行(さんぎょう、さんこう)
登山をする行為のこと。山に行くという意味合いと、山で行(ぎょう)をするという意味合いがある。
・山座同定(さんざどうてい)
山頂から周囲に見える山をコンパスや地図などと照らし合わせて展望すること。
・三点確保
一般の登高や岩登りなどにおいて、四肢のうち、常に三肢が地面などに固定されている状態を保つこと。
・三点支持
三点確保のこと。
し
・シール
山スキーで歩行する場合、スキーが後戻りしないようにするため、スキーの滑走面に装着するもの。現在は化繊やモヘヤ(ヤギの毛)製が多いが、元はアザラシ(英語でシール)の毛皮を使用していた。
・GPS
グル―バルポジショニングシステム。米国のGNSS(衛星測位システム)であり、軍事用であるが、広く民間でも利用されている。GNSSには、GPS(米国)のほかに、QZSS(みちびき、日本)、Galileo(EU)、GLONASS(ロシア)、北斗(Beidou、BDS、中国)などがある。
・自在
ランナー。テントの張り綱の長さを調整するための部品。
・シャフト
ピッケルの柄の部分。
・シャワークライミング
沢登りで、滝の中を登るルートを取ること。
・ジャンクションピーク(JP)
稜線上を縦走している時に、ルートの分岐点になる山の頂上。
・縦走
複数の山頂を踏破して別の登山口に下山すること。
縦走路を折り返して元の登山口に戻ることをピストン縦走と呼んでいる。
・重登山靴
オールシーズンに対応できる、頑丈な登山靴。
・シュラフ
寝袋。スリーピングバッグ。
・シュラフカバー
シュラフを防寒、防水するためのカバー。ナイロンやゴアテックス製がある。
・背負子(しょいこ)
フレームにショルダーベルトだけという伝統的な搬送道具。ザックに入らないような大きな荷物などをロープでフレームに固定して背負う。
・ショートスパッツ
足首だけの短いスパッツ(ゲイター)。主に夏山において、登山靴に石ころなどが入らないよう靴に装着する。
す
・スイスアーミー
スイスのビクトリノックス製軍用ナイフで、いわゆる小型のアウトドア用10徳ナイフ。
登山家や冬山愛好家が好んで使用する。
・ストーブ
キャンプ用携帯コンロのこと。
ガス式が主流であるが、ガソリン、灯油式もある。
・スノーシュー
深雪を歩行するための大型の洋式かんじき。
わかん(輪かんじき)と違い、浮力が大きく、かかとが可動するため歩きやすい。
・スノーショベル(スノースコップ)
雪山で使用する小型の登山用携帯スコップ。雪洞、イグルー、防風壁の構築、除雪、雪崩埋没者の捜索など多用途。
・スノーソー
雪や氷を切り出すためののこぎり。イグルー作成などのために使用される。
・スノーブリッジ
雪山において、雪の下に沢が流れている場所は、徐々に下の方の雪が融け、橋状になるが、そのような場所を言う。
・スピッツェ
ピッケルのシャフトの先端部。石突き。
・スラブ
岩登りにおいて、登りづらい1枚岩のこと。
・スリーピングバック
寝袋。シュラフ。
せ
・雪渓
残雪が沢地形の中に残っている場所。
・雪庇(せっぴ)
雪山において、稜線の風下に雪が庇のようにせり出した危険な場所。
・雪盲(せつもう)
ゆきめ。雪山において、強い紫外線によって目に炎症を起こしてしまうこと。
・全荷(ぜんに)
泊を伴う登山の場合に、テントや炊事道具、食料などを必要な装備すべてを大型ザックに詰め込んだ状態。
そ
・遡行(そこう)
沢登りにおいて上流に向かって登ること。沢を歩くことそのものを遡行とも呼んだりもする。
・外張り
冬山において、ダブルウォールテントの上を覆う防寒防風のための冬用フライシート。
・ソフトシェル
防風・防寒用の登山用アウター。ハードシェルと違い、防水性はない。
・ゾンデ(プローブ)
雪崩発生後に埋没者を捜索するための細長い棒。雪面に刺して埋没者を捜索する。
・ゾンメルスキー
深雪の雪上歩行専用に作られたスキー。一般的なスキーよりも幅広で、ソールにはシール(アザラシの毛皮など)が貼り付けてあり、ビンディングは踵が固定されていない。ゾンメル、ゾンベルなどと呼ばれる。