登山に適した水筒の選び方とは
水筒には、大きさ、材質、形状など様々なものがあります。
それぞれの特徴を理解して使い分けることになりますが、登山においては、「ナルゲンボトル」に代表される、丈夫で、口が広いタイプの水筒の利用者が多くなっています。
今回は、登山に適した水筒について紹介します。
登山用水筒の代名詞、ナルゲンボトルの特徴とは
ナルゲンボトルは、アメリカで開発されたプラスチック製の水筒で、世界中の登山家などに愛用者が多いとされる、アウトドアではメジャーな水筒です。

ナルゲン1L用広口ボトル
ナルゲンボトルのサイズには、0.5L、1L、1.5Lなどがあり、また、形状は広口ボトルが主流ですが、飲みやすい細口ボトルなどもあります。
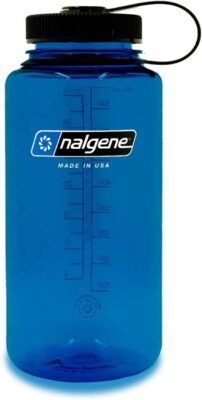
アマゾン ナルゲン Nalgene 広口1.0L Tritan Renew
楽天 ナルゲン Nalgene 広口1.0L Tritan Renew
登山に使用する場合、容量や形状などを考えると、1L用の広口ボトルが使い勝手が良いと思います。
これを登山に必要な本数分用意します。
ナルゲンボトルは色のラインナップが豊富なので、ボトルの色を違わせることで、飲み物の中身をわかりやすくすることなどもできます。

ボトルのカラーは豊富。
1L用ボトルは、なみなみに水を入れると1.2L程度入ります。
山では水は貴重なので、一杯まで入れますが、ナルゲンのフタは昔から液漏れしなことで有名です。
フタは一般的な、ネジ山で締め込んで、フタ裏のパッキンで密閉するタイプではありません。
フタ裏にパッキンはなく、ネジ山の密着だけで密閉することができる特殊な構造になっています。
適度な力でフタを締めるだけで絶対に液漏れしません。
登山においては、大きな信頼感です。
筆者は20年以上ナルゲンを使用していますが、経年使用でフタがあまくなったり、液漏れを起こしたことは一度もありません。
ボトルは頑丈で、耐久性は抜群です。

ナルゲンボトルのフタ。パッキンがなく特殊なネジ山。
ボトルが広口になっているのも登山では適しています。
広口ボトルは、水深の浅い沢でも水が汲みやすいですし、沢水を煮沸したあと、コッヘルから水を移す時にも、口が広いので便利です。
スポーツドリンクの粉なども入れやすいです。
口が広いので中が洗いやすくて清潔です。
口が広く、密閉性が高いので、防水の目的で行動食や雑貨などを入れることもできます。

登山において、広い口は何かと使いやすい。
ボトル本体の材質ですが、当初はPC(ポリカーボネード)を使用していましたが、現在では、BPAフリー(人体に影響があるとされるビスフェノールAを含まない)である、飽和ポリエステル樹脂を使用しており、耐熱温度はー20℃~100℃、フタの材質はPP(ポリプロピレン)で、耐熱温度は0℃~100℃となっています。
煮沸したばかりの熱湯を入れても大丈夫ですし、凍らしても大丈夫です。
冬山などでは、雪を煮沸したお湯を入れたナルゲンを寝袋に入れると、とても温かく、湯たんぽの代わりになります。
フタに脱落防止用のループが付いていますが、ここをつかんで持っても、すぐに緩んだり、ちぎれたりはしません。(※ループをカラビナなどにぶら下げての長時間の移動はおすすめしません。)

フタに付いているループ。
ひとつだけ注文を付けるとすれば、本体の材質は無臭ですが、フタはポリプロピレンなので、ややにおいがします。
ですが、他社の同等品の水筒のフタもポリプロピレンなので、そのあたりは気にしないことにします。
このように、登山用の水筒として、ナルゲンは丈夫で扱いやすく、汎用性が高い形になっていると言えます。
ほかにはこんな水筒も
水筒には、ナルゲンのようなプラスチックタイプのほかに、アルミやステンレスなどの金属タイプ、折りたためるソフトタイプ、長いストローがついたハイドレーションタイプなどがあります。
金属タイプ~アルミ製
アルミ製の水筒は長い歴史があります。
軽さと、丈夫さ、においがしない、スタイリッシュなどの点では、プラスチックタイプを凌ぎます。
アルミ製のほとんどの水筒は、基本的に保温性はありません。
アルミ製は丈夫ですが、ぶつけると、へこむので注意が必要です。

アマゾン シグ(SIGG) アウトドア 水筒 軽量 スイス製アルミボトル
楽天 シグ(SIGG) アウトドア 水筒 軽量 スイス製アルミボトル
金属タイプ~ステンレス製
ステンレスタイプのほとんどは、サーモス(テルモス)に代表される魔法瓶です。
体が冷えて温かい飲みのもがほしい時や、熱湯を入れて行けば、頂上でカップめんを作ることもできます。

アマゾン サーモス 山専用ステンレスボトル900ml FFX-901
楽天 サーモス 山専用ステンレスボトル900ml FFX-901
プラスチックタイプ
前述説明したナルゲンボトルです。
モンベルなどでも、似たような形状の商品が販売されています。
このシンプルな形が山では汎用性があり、洗浄も簡単で清潔、丈夫で長持ちします。
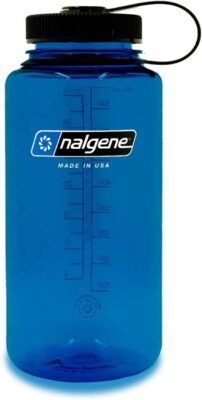
アマゾン ナルゲン Nalgene 広口1.0L Tritan Renew
楽天 ナルゲン Nalgene 広口1.0L Tritan Renew
ソフトタイプ
ソフトタイプは軽くて、使用後は折りたためるという利点があります。
プラスチックタイプや金属タイプに比べると当然耐久性がなく、経年使用で穴が開きますので、登山に使用する場合は、出発前によく点検し、使い古しのようなものは使用しないようにします。
耐久性はともかく、水場の少ない縦走登山などで水を大量に背負わなければならない場合など、荷物を少しでも軽くしたい場合にはソフトタイプが断然有利です。
大きさは1L程度のものから大容量のものまであります。

アマゾン Platypus(プラティパス) プラティ 2L 25601
楽天 Platypus(プラティパス) プラティ 2L 25601
ハイドレーションタイプ
トレイルランをやる人など、止まって休憩しないような登山スタイルに適しています。
最近では、ハイドレーションが使えるように小さな穴が開いているザックを多く見かけますが、一般的に、ザックから水筒を取り出す余裕もないような登山スタイルは、トレラン以外にはありませんので、ハイドレーションを積極的に登山に使用する機会は少ないと思います。
熱中症対策などのために、歩きながら小まめに吸水したい場合などには便利だと思います。

アマゾン Platypus(プラティパス) ビッグジップ EVO
楽天 Platypus(プラティパス) ビッグジップ EVO
登山には何リットル持って行く?
1日の登山で飲む水の量ですが、計算方法には諸説あります。
水が多すぎれば、ザックが重たくなりますし、足りなければ、脱水や熱中症を引き起こしやすくなります。
真夏の登山を例にあげると、熱中症対策のためには気温などにもよりますが、30分に200ml程度の給水が必要になるとされているので、1時間に400ml程度は必要となり、次のような式になります。
・400×行動時間=必要な給水量(ml)
例えば、下山まで5時間程度の山なら、「400ml×5時間=2000」ですので、2Lは必要になります。
このほかに、次のような計算式もあります。
・5×体重(kg)×行動時間=必要な給水量(ml)
この計算式では、体重60kgの人が5時間登山をすると、5×60kg×5時間=1500mlですので、1.5Lは必要になります。
山で飲む水の量は、気温で大きく変わり、また、登山者の体調や年齢などでも変わります。(給水は若い人ほど少なく、高齢者ほど多く必要になる。)
春や秋など比較的寒い時期には、真夏の半分かそれ以下しか水を飲まないこともあります。
汗をあまりかかない人、汗っかきな人など、発汗量は個人差がありますが、上記を参考に計算してみて、自分が必要な水の量を決定すると良いと思います。
筆者の経験上、個人差はあると思いますが、上記の式は必要最低量と考えた方が良いと思います。
熱中症にかかった場合、水が足りないと、行動中に回復できる見込みがなくなりますので、水の量の決定は慎重に行う必要があります。(熱中症の対策について詳しくは「登山の熱中症対策!水分・塩分・糖分・ミネラルをとれ!」を読んでみて下さい。)
まとめ
日帰り登山では、ペットボトルを使っている人が多いと思います。
ペットボトルは水筒ほど丈夫ではありませんが、軽くて、それなりの強度があります。
日帰り登山が多い場合は、水筒は必要ないのかも知れませんが、年間山行日数が多い場合や、泊を伴う山行などの場合は、丈夫な水筒を用意した方が便利だと思います。
タフな作りで、一度買うと、とんでもなく長持ちする、ナルゲンボトルは特におすすめです。
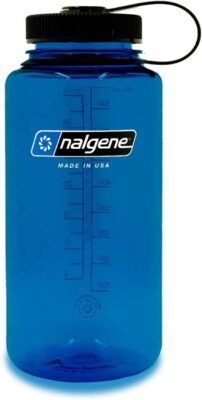
アマゾン ナルゲン Nalgene 広口1.0L Tritan Renew
楽天 ナルゲン Nalgene 広口1.0L Tritan Renew
.png)
- 登山装備関連記事
- 登山靴の種類
- 登山靴の選び方のまとめ(前編)
- 登山靴の選び方のまとめ(後編)
- ザック選びの基本1~キスリングからアタックザックへ
- ザック選びの基本2~ザックの種類と選び方
- 登山の服装選びの基本1
- 登山の服装選びの基本2
- 登山用レインウエア(カッパ)の選び方~透湿性だけで選ぶと失敗する
- ゲイターの選び方。ショートスパッツ、ロングスパッツ



